優しいママほど陥りやすい“関わりすぎ”。
エピソードと共に考えてみませんか?
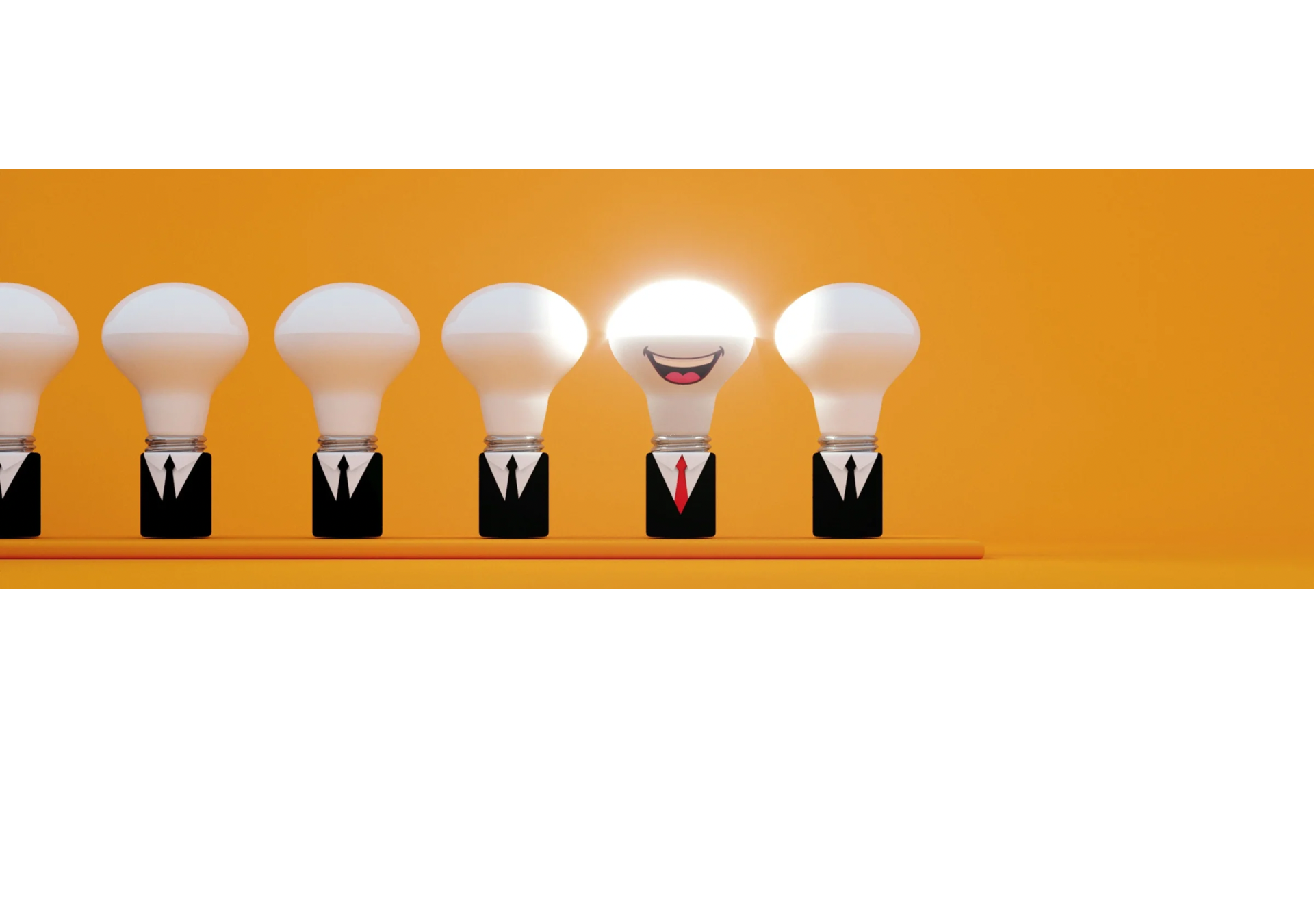
この記事では、過干渉・過保護のサインと
改善のヒントを紹介します。
実際のエピソードを交えながら、
どう関われば子どもが伸びていくのか、
一緒に考えてみましょう。
気づかぬうちに「過干渉・過保護」に
なってない?

愛情と干渉は紙一重
「子どものために」と思ってやっていることが、
いつの間にか子どもの成長を妨げてしまうことが
あります。
- 勉強や宿題を全部チェックする
- 友達関係に口を出しすぎる
- 子どもの代わりにすぐ動いてしまう
これらは親の愛情の裏返し。
でも、やりすぎると「子どもの自立」を奪って
しまうのです。
気づきにくいのは「ママの優しさ」から
始まっているから
過干渉・過保護は、決して“悪いママ”の行動では
ありません。
むしろ「子どもを守りたい」「失敗させたくない」という優しい気持ちから生まれるもの。
だからこそ、気づきにくいんです。
でも、気づいた瞬間から変われます✨
そのときはラクに見えても、あとで
困る日が来る

親が先回りすると「安心」だけど…
過干渉・過保護は、実は子どもにとって
その瞬間はラクなんです。
- 困ったときに親がすぐ答えをくれる
- やらなくても親が動いてくれる
- 自分で考えなくても済む
そのときは「安心」「快適」かもしれません。
でも、ずっとそれが続くと
“あとでツケが回ってくる” んです。
育ちにくくなる力たち
- 自立心(自分で決める力)
- 考える力(試行錯誤する力)
- 挑戦力(失敗しても立ち上がる力)
- 自己肯定感(やればできる!という感覚)
- 満足感(自分でやり切った喜び)
どれも大切な「生きる力」。
ちょっとした失敗や試行錯誤を経験することが、
栄養になるんです🌱
なぜ過干渉・過保護は逆効果に
なるの?

子どもが自分で考えなくなる
⚫️親が先に手を出す
⚫️答えを与えてしまう
→ 子どもは「どうせママがやってくれる」と
思い、自分で考える力が育ちません。
親の期待に応えようと無理をする
過保護に育つと、子どもは
「親のために頑張らなきゃ」と思い込みます。
その結果、自己否定や不登校のきっかけに
なることも…。
「過干渉・過保護」サインチェック
イエローカードになる前に⚠️

ママのあるある行動リスト
⬜︎子どもの成績に一喜一憂してしまう
⬜︎学校の先生にすぐ連絡したくなる
⬜︎友達とのトラブルを先回りして解決
しようとする
⬜︎子どもの失敗が、自分の失敗のように
感じる
これらが続くと、イエローカード🟨です。
レッドカード🟥になる前に、一度立ち止まって
深呼吸してみましょう。
じゃあ、どうしたらいい?
- できることは「見守る」
- 手を出したくなったら「一拍おいて考える」
- 子どもが自分で解決できたときは、思いっきり褒める
“信じて待つ勇気”が、
子どもを大きく育てます。
ママから届いた声

息子さんが高校入学後に学校へ
行けなくなり、どうしたらよいか
分からなかったママ。
「親子関係が原因では?」という言葉に
ハッとして、過保護・過干渉に気づかれた
そうです。
息子さんは高校を辞める選択をしましたが、今は通信制高校に通いながら、
前向きに笑顔を取り戻しました。
バイトを始め、家族で出かける時間も
増えたとのこと。
「気づかせてもらえて本当に有難かった」
そんな感謝の声をいただきました🌸
エピソードから学んだこと

かめちゃんの気づきシェア
そのママと関わらせてもらったときに、
私もいろいろ学ばせていただきました。
過干渉・過保護に気づかずに続けて
しまうと、子どもはだんだん不安定に
なってしまうことがあるんです。
高校選びの大事な場面でも、親子で本音を
話せずにすれ違ってしまったそう…。
不登校・発達障害・転学と、
いくつもの困難を経験…。
それでもママは最後に
「ママが変われば、子どもも変わる」を
実感し、心のシフトチェンジしましたと
笑顔で話してくれました。
大切なのは“これからどう関わるか”。
あなたも今日から、一歩を踏み出せば
大丈夫だよ😊
ここまで読んでくれたあなたへ
最後まで読んでくださって、ありがとう
ございました🌸
もし「これ、わたしのことかも」と思ったら、
ぜひ いいねやコメントで教えていただけると
嬉しいです😊
あなたの思春期子育てが、ラクであたたかい
時間になりますように💕



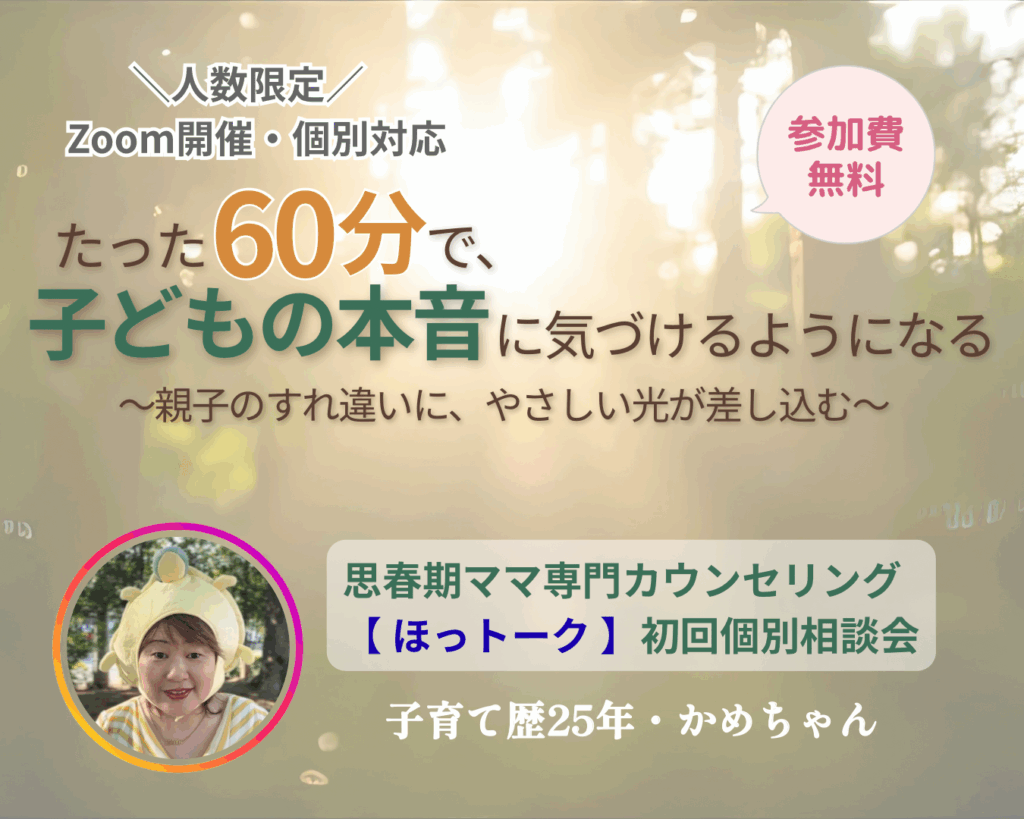
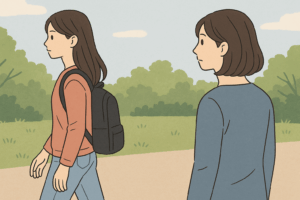

コメント